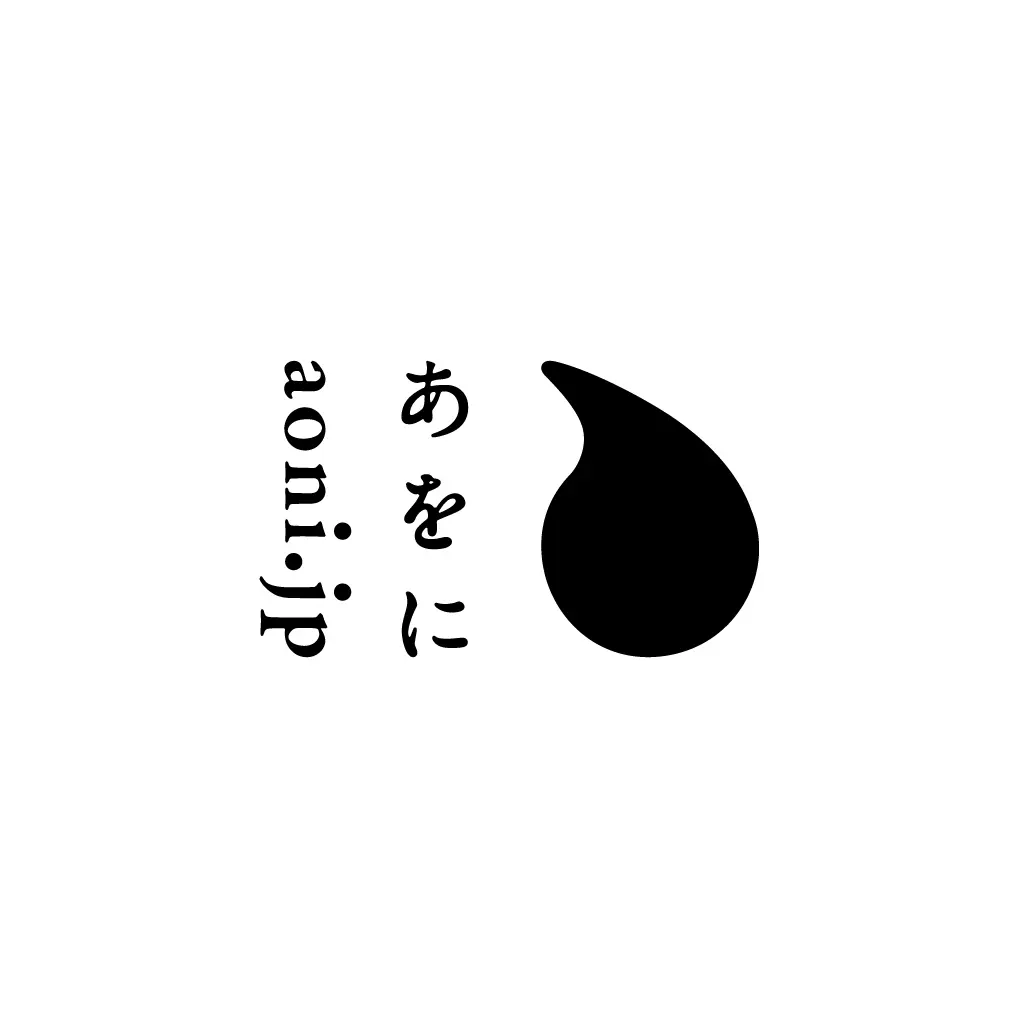「クラウドファンディングのやり方がわからない」
「相談する人がいないから、自分一人でやらないといけいない」
「クラウドファンディングを始める前に情報を一から集める必要がある」
かつての筆者も同じでした。
初めてクラウドファンディングのページ作成をしたのが2014年。その時は今以上に相談する人や企業、情報もありません。
まず何を決める、どこでやる、誰に相談すればいい、筆者でもクラウドファンディングができるのかと不安でした。
クラウドファンディングのホームページを見て仕組みは理解できた。でも、仕組みではなくやり方がわからない。
当時のセミナーは仕組みの説明や内容が多く、プロジェクト制作経験者によるやり方はあまりなかったように思います(2016年時のお話)。
クラウドファンディングの仕組みを初めに理解しておくべきです。しかし、実際にやってみようと思ったら、やり方を知りたい!と皆さんも思われるのではないでしょうか。
その後プロジェクトページ制作を重ねて、クラウドファンディングのやり方をトライアンドエラーを繰り返しながら、日々勉強することになりました。

今から紹介するクラウドファンディングのやり方で大切なことは、クラウドファンディングの全体を把握しなければいい結果につながらないということ。
目標を考え、サイト(プラットフォーム)を選び、クラウドファンディングを実施するメリット・デメリット、そして何より支援者のことを考える。
約80プロジェクト以上のクラウドファンディングページ制作に携わって深まった知識が、クラウドファンディングに初めて挑戦される方の解決につながれば。
この記事ではクラウドファンディングのやり方の手順を徹底的に解説し、夢へ挑戦する可能性にご活用ください。
また、クラウドファンディングのやり方に関する基本知識をわかりやすく解説します。
クラウドファンディングに挑戦
記事に迷ったら上から順にお読みください
- クラウドファンディングの意味とは?【保存版】基本用語もわかりやすく解説
- クラウドファンディングの仕組みとは?を簡単に解説!
- 融資とクラウドファンディングの違い!知っておくべき資金調達
- 寄付型クラウドファンディングと寄付の違いとは?それぞれの特徴を分かりやすく解説
- クラウドファンディング市場規模!国内調査
- クラウドファンディングサイトのおすすめは?
- クラウドファンディングサイトをタイプ別に徹底比較!おすすめサイトは?
- クラウドファンディングのメリットとは!【必見】失敗しないコツ7つ
- クラウドファンディングのデメリットを最小限にする方法とは?【徹底解説】
- クラウドファンディングは難しい?意味を理解しないと失敗する理由
- クラウドファンディングの成功例!プロジェクトを達成する極意
- クラウドファンディングのやり方とは?始め方のコツを10の方法で解説
- クラウドファンディングにコンサルタントは必要?選び方7つのポイント
- クラウドファンディング代行は依頼するべき?費用やサポート内容をチェック
- クラウドファンディングをビジネスで活用【注目】成功事例をまじえて解説!
- クラウドファンディングの見返りを学ぼう!タイプ別の仕組みから注意点まで
- クラウドファンディングのリターン(お返し)の相場は?ポイントを解説
- クラウドファンディングのリターンなしとは?【寄付型の実行&支援
- クラウドファンディングで商品を購入する方法【簡単・安全】
- クラウドファンディングの成功率を高める!失敗例から施策まで解説!
- クラウドファンディングページ作成!読みたくなる3つのコツ
- クラウドファンディングが達成しなかったら?【プロが教える】5つのリスクへの備え方
- クラウドファンディングでトラブルを回避するための基礎知識と具体事例
- クラウドファンディングで確定申告は必要?
クラウドファンディングのやり方10ステップ

クラウドファンディングのやり方のポイントは、
- 「目標を考える」
- 「種類を選ぶ」
- 「サイトを選ぶ」
- 「キュレーターに相談する」
- 「ページを作成する」
- 「審査・公開」
- 「広報活動をする」
- 「活動報告をする」
- 「お礼」
- 「リターン」
の10ステップです。
ここでは購入型クラウドファンディングサイトのやり方を中心に、それぞれのノウハウを解説していきます。
また筆者は購入型クラウドファンディングサイトMakuakeにて、約80プロジェクトを実施しました。その経験も合わせてお伝えいたします。
Makuake以外のクラウドファンディングサイトでも大まかな基本の流れは変わりません。やり方は個人も法人も同じです。
大きな成果を上げたいのであれば、プロジェクトの流れを把握することはとても重要です。知識がまったくなくてもこのステップを理解すれば、初心者でも安心してプロジェクトを実施できるようになります。
プロジェクトの目標を考える
1つ目に、クラウドファンディングの目標を考えます。
結論から、10ステップの中でここが一番重要です。なぜなら、クラウドファンディングのやり方として、あなたがやりたいことを明確にしなければ支援者に想いや熱意が届かないからです。
初心者の多くはどうやるかの手段や方法で悩みます。しかし、クラウドファンディングでは、なぜそれをやるのかが重要であり、手段や方法はその次です。
例:
なぜ資金の調達をしたいのか。
なぜクラウドファンディングで支援者を募集するのか。
クラウドファンディングでなければならない理由は。
目標に対する想いが伝わらなければ支援者に共感してもらえず、一般的な商品販売サイトと変わりません。
クラウドファンディングは一般的な販売サイトとは違い、実行者と支援者の共感がエネルギーとなり大きな達成へと繋がります。したがって、クラウドファンディングの目標がブレてしまっては共感が生まれず、結果はどうやってもうまくいきません。
なぜクラウドファンディングでやるのか。その結果、どのような目標を達成するのかなどをしっかり考えて起案しましょう。
クラウドファンディングの種類を選ぶ
2つ目に、クラウドファンディングのやり方を選びます。
クラウドファンディングは、「投資・融資型」「購入型」「寄付型」と3つに分けられます。
「投資・融資型」「購入型」「寄付型」の大きな違いはリターンの内容です。
- 投資・融資・株式型
-
出資者が金銭的リターンを受け取る
- 購入型
-
支援者が商品・サービスのリターンを受け取る
- 寄付型
-
支援者は基本的にリターンを受け取らない(例外あり)
投資・融資・株式型は、利子や分配金などのリターンが発生するタイプのクラウドファンディング。購入型は商品やサービスがリターン。寄付型は募金やプロジェクトに対する寄付がリターンとなります。
ただし寄付型でも、お礼として商品やサービスなどのリターンを作る場合もあります。
最近のクラウドファンディングには、ふるさと納税の仕組みも取り入れた税金の控除対象になるものも増えました。
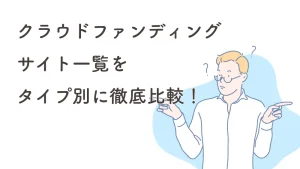
この記事では初心者でも挑戦しやすい「購入型」「寄付型」を取り上げていきます。
クラウドファンディングサイトを選ぶ
3つ目にサイト(プラットフォーム)を選びます。
クラウドファンディングには、「クラウドファンディングサイトを利用する」もしくは、「クラウドファンディングのシステムを自社サイトに導入する」の2種類の方法があります。
初めて個人や法人でクラウドファンディングをするなら、『クラウドファンディングサイトを利用する』を選んでください。なぜなら、インターネットで支援者を募る場合、サイトの訪問者数や会員数が重要となるためです。
プロジェクトを広めるには、できる限り多くの方に見てもらう必要があります。また実行者と支援者の管理をサイトに任せることにより、プロジェクトに集中ができ、お金(資金)に関するリスクも抑えられます。
購入型、寄付型のクラウドファンディングサイトは数多くあり、各サイトの違いは、
- 支援されやすい分野
- 手数料
大きくはこの2つに違いがあります。
ここでは購入型・寄付型クラウドファンディングとして有名な3つのサイトをご紹介します。
- CAMFIRE(キャンプファイヤー)
-
国内最大クラウドファンディングサイト。融資・購入・寄付とさまざまなジャンルが用意されている。
- Makuake(マクアケ)
-
国内資金調達金額No.1のプロジェクトが生まれるなど、購入型クラウドファンディングに特化したクラウドファンディングサイト。2019年12月に上場し、クラウドファンディングではなく0次流通市場を提供。支援ではなく、応援購入に。
- READY FOR(レディーフォー)
-
日本で初めてクラウドファンディングのサービスを開始した購入型および寄付型のクラウドファンディング。
この3つ以外にも日本にはたくさんのクラウドファンディングサイトがあります。運営方針によって魅力はさまざまです。
魅力が感じる運営会社をチェックし、比較しながら検討してください。
これ以降のやり方については、筆者が数多くプロジェクトを実施したMakuakeをベースにお伝えします。
やり方の基本はどこのサイトも同じなので、Makuake以外でもご活用ください。
キュレーターに相談する
4つ目に、プロジェクトを始める第一歩となる「サイトへの登録と問い合わせ」になります。
クラウドファンディングの認知が広まったことから問い合わせが急増しており、実施する内容の詳細を問い合わせに記載しなければなりません。
問い合わせ後、順調に進めば各地域運営担当のキュレーターから連絡があります。
キュレーターと一緒に、
- 今後の掲載スケジュール
- いつ頃スタートができるのか
- ページを作成の提出日、など
実行日を基準に逆算したスケジュールを組んでいきます。
その他にもプロジェクトを成功させるためのノウハウや、具体的な施策、過去の事例など、さまざまなアドバイスを教えるでしょう。とはいえキュレーターはたくさんのプロジェクトを抱えているため、相談時間も限られています。
質問の前に一般的な知識はつけておき、わからない部分のみ相談することをオススメします。
プロジェクトページを作成する
クラウドファンディングのやり方5つ目は、プロジェクトページを作成になります。
クラウドファンディングサイトでは、プロジェクトごとにページを作成します。
作成方法はサイトによって多少の違いはありますが、ブログ記事の作成ができれば問題ありません。アメーバブログ経験者であれば、Makuakeのプロジェクトページはとても簡単です。
ページには文章、イラスト、写真、動画などを掲載していきます。
ここで10ステップの1つ目が役にたちます。あなたがなぜこのプロジェクトをしたいのかを伝え、思わず共感してしまうページを作成しましょう。
ページ作成については、他の記事にまとめています。

もしページ制作に悩んだなら、支援者の目線や気持ちになってみてください。支援者はなぜ商品やサービスを支援するか。その気持ちを考えるだけでも、ページの見せ方が変わるかもしれません。
プロジェクトの審査・公開
6つ目は審査です。プロジェクト公開までに複数回の審査があります。
Makuakeでは、プロジェクト公開の約2〜3週間前に初回申請をしなければなりません。この時点でプロジェクトページの本筋ができていると順調です。
その後はページ制作の進み具合により、審査や掲載日のスケジュール変更の調整がされます。
ただし何度も日程変更をするとキュレーターへの印象も悪くなるため、なるべく余裕をもったスケジュール管理と制作を心がけましょう。
また公開するまで安心はできません。プロジェクトの内容によっては、大幅に作り変えることがあります。理由としては、広告表記に関する内容として「薬機法」が厳しくなったためです。
- 世界一
- 日本一
- 安心
- 安全
- アレルギーなど
上記の表記を使用する場合、プロジェクト内容によってはエビデンスの準備が必要となります。
エビデンスはクラウドファンディングサイトの法務部に提出し、担当者が確認します。エビデンスがない場合は表記の削除、もしくは、エビデンスの準備による掲載延期もあるため、十二分に注意しましょう。
プロジェクトの広告・広報活動をする
クラウドファンディングのやり方7つ目は広告・広報活動です。
過去の経験を振り返ると、広告・広報活動をしている、していないでは、クラウドファンディングの結果が大きく変わります。
初めての実行者はプロジェクトページ制作に追われ広告・広報活動を後回しにしていますが、制作と同じく広告・広報活動も同時進行で進めなければなりません。
なぜなら、クラウドファンディングのやり方3つ目と同じく、できる限り多くの方にクラウドファンディングを知ってもらう必要があるからです。
したがって、キュレーターにどこまでの情報をSNSやホームページに公開していいかなどを相談し、またプロジェクト公開日が決まっているのであれば、見込み支援者に随時情報の発信をオススメします。
プロジェクトの活動報告をする
8つ目からはプロジェクト掲載後の対応になります。
クラウドファンディングの多くは、掲載スタートから支援者の手元に商品・サービスが届くまで数か月の期間がかかります。活動報告は支援者との関係性を良好にしてくれるでしょう。また、実行者の活動が支援に悩んでいる人への後押しにもなります。
どのような内容を送るかは決まりがありません。他のプロジェクトを参考にするのもひとつです。
プロジェクト支援者へのお礼
プロジェクトのやり方9つ目は、支援者に対するお礼です。
支援者はプロジェクトに対するコメントを任意で記載できます(コメント必須のサイトもあり)。
「がんばってください!」「楽しみにしています!」といった応援コメントや、商品に対する今後の期待などのコメントが投稿されます。
支援者からのコメントは、実行者が支援者とつながるコミュニケーションツールです。すべてのコメントに返信するのは大変ですが、漏れがないように返信してください。
また支援者自身がSNSやブログなどでプロジェクトを共有してくれることもあります。そのような場合もできる限りお礼のメールやメッセージを送ってください。
クラウドファンディングでは共感が大きな力になることを忘れないでください。そのためにお礼はとても大切なことです。
支援者がクラウドファンディングでどのように購入しているかはこちらを参考にしてください。

プロジェクト終了後に商品やサービスのリターン
最後は商品やサービスのリターンです。
プロジェクト終了後、支援者の情報をもとに商品の発送やサービスの提供をおこないます。
過去に筆者もさまざまなプロジェクトに支援をしましたが、商品だけ送ってくる実行者もいれば、お礼の手紙や、今後のプロモーションも兼ねたSNS・ホームページの紹介のチラシなどの同封もあります。
発送や提供が終わったらクラウドファンディングの終了ではなく、今後も繋がってもらえる方法を考えてみましょう。
クラウドファンディング事前準備のコツ

ここまでクラウドファンディングのやり方10ステップを解説しました。初めてクラウドファンディングに挑戦する個人や法人の方にも流れが掴めたのではないでしょうか。
しかし、初めての方の多くは「達成できるかな?」「支援が集まるかな?」といった不安がつきものです。
そのような不安を少しでも解消していただけるために、過去の経験に基づいた「達成率が上がる事前準備のコツ」をあわせてご紹介します。
一人よりチーム
クラウドファンディングの制作は1人でされる方が多いです。制作に関しては1人でも問題ありません。筆者も文章以外を一人で担当しています。
しかし、クラウドファンディングのやり方7つ目に解説した「プロジェクトの広告・広報活動をする」は個人より複数人をオススメします。
なぜならプロジェクトをより多くの人に知ってもらうには、プロジェクトを拡散しなければなりません。その場合、一人での拡散力では限界が生じます。
したがって、クラウドファンディングの目標に共感してくれる仲間を集め、個々のSNSや情報網でプロジェクトの共有をお願いします。
制作は個人でも構いませんが、広告・広報活動はチーム力と心掛けてください。
ランディングページ(LP)作成
ランディングページの目的は、「クラウドファンディングをする」を広めるための媒体です。
基本的には、クラウドファンディングのプロジェクトページ内容を掲載前に公開することができません。そこでランディングページでは、いつ、どこでなどの内容をまとめて公開します。
事前にいつ、どこでプロジェクトがスタートするかがわかっていると、初日に支援しれくれるかもしれません。重要なのは、興味がある人に知ってもらうことです。
ほかにも、LINEやメルマガなどの登録にうながし、広報活動に活用する方もおられます。
ランディングページを作成する場合は、あらかじめキュレーターに相談してください。キュレーターはさまざまな情報を持っているので、あなたの参考になるサイトを教えてくれることもあります。
SNS活動
上記のランディングページの作成が難しい人は、SNSで広報活動をしてください。
筆者のオススメは「Instagram」です。
インスタグラムは画像と文章のバランスがよく、ハッシュタグによる検索も狙えます。またフォロワーの投稿やストーリーで共有してもらえると、情報の拡散も狙えるためです。
そのほかにも拡散力であれば「Twitter」、より身近な人であれば「Facebook」など、SNSを使い分けて広報活動をしてください。
クラウドファンディングによくある質問と回答

いくらやり方がわかったといっても、それでも悩みはつきません。
そこで、ここでは筆者に寄せられるクラウドファンディングを始める前に関する質問とその回答をご紹介します。
クラウドファンディングは個人向け?企業向け?
結論から申し上げると、とくに考える必要はありません。個人でも成功しているプロジェクトはありますし、企業だからといって成功するわけではありません。事業者は問わないです。
ただし、プラットフォームによっては個人の傾向が強い・企業の傾向が強いといった印象はあります。
クラウドファンディングサイトはどこがいいですか
クラウドファンディングサイトには個々の特徴があります。どこがいいかは一丸に言えません。それでも迷う場合は有名なサイトをオススメします。
理由は
- サイトの会員数、流入数が多い
- 実績が多く、参考になる事例が多い
- 行政と協力している
初めてクラウドファンディングをするのであれば、余計な不安はできる限りない方が望ましいです。
また有名なサイトであれば随時無料セミナーを実施しているので、参加してみるのもいかがでしょうか。
クラウドファンディングを公開するまでどれくらいかかりますか
筆者の場合、約1か月半から2か月とお伝えします。
しかし、これは制作が順調に進んだ場合です。準備が遅れてしまえば延期になります。初めての方であれば3か月は余裕をみてください。
プロジェクト制作はどのようにすればよいですか
クラウドファンディングを公開するにあたり最低限必要なのは、文章と画像です。画像は写真でもイラストでも構いませんし、動画は必須ではありません。
しかし、支援者に想いを届けたいのであれば「最後まで読みたくなるページを作成」してください。
また、日頃の業務に追われ、なかなかページ制作ができない。想いをとどけるような文章が書けない。キレイな写真が用意できないといった悩みもあります。その場合は外部に依頼されることをオススメします。
筆者であれば無料相談をご用意しております。ホームページからお問い合わせが可能です。よければご利用ください。
クラウドファンディングの広告・広報活動の準備はいつからすればよいですか
クラウドファンディング達成率が上がる事前準備のコツと重複しますが、広報活動は早い段階からされることをオススメします。
最近では1年前から準備しているプロジェクトも。そういったプロジェクトは大きな成果を上げています。初めての方はプロジェクトスタートが始まりと思われていますが、事前準備の広報活動が本当の始まりです。
クラウドファンディングをすると決めた段階で広報活動をしてください。コツとしては一気に情報公開をせず、少しずつ継続していくことです。
クラウドファンディングのリターンは何がよいでしょうか
クラウドファンディングのやり方1つ目の目標にそったものです。
たとえば、目標が新商品のプロモーションであれば、商品そのものがリターンになります。資金調達であれば商品単品や、複数などの組み合わせを考えてもよいでしょう。
筆者がリターンを考えるときに大切にするのは、ブレないことです。目標からブレてしまうとなんのためのクラウドファンディングかわからなくなります。
目標金額の設定はいくらにすればよいですか
目標金額は自由に設定できます。またサイトによって異なりますが、Makuakeであれば、All in、All or Nothingを選べます(サイトによる)。
| 選択項目 | 目標金額達成 | プロジェクト実施 |
|---|---|---|
| All or Nothin | しない | しない |
| All in | しない | する |
したがって目標金額を考える前に、どちらにするかによって設定金額は変わります。
All or Nothing であればプロジェクトを実施しない=目標金額となるため、ご希望の目標金額を設定してください。
All in であれば、筆者の場合、実行者にリターンの金額と個数を目安に何割達成できればいいかを伺い、その達成率が100%になる金額を目標金額としてご提案します。
例:
リターン 1個 1,000円、在庫 100個、目標達成 50%
1,000 x 100 = 100,000 x 50% = 50,000円
目標金額 50,000円
とはいえ、商品の仕入代、金型代など内容はさまざまなので、それらを元に考えるのも方法です。
ただし目標金額が高すぎると達成率が低くなり、あまり支援されていないように見えてしまいます。また反対に目標金額が低すぎて達成率が高すぎると、そもそも目標金額って何?となってしまいます。これらは心理的なものと考えています。
どうしても悩んだ場合はキュレーターに相談しましょう。
クラウドファンディングのやり方のまとめ
プロジェクトのやり方はどこのクラウドファンディングサイトもほとんど同じです。しかし、目標を達成するには事前準備や余裕をもったスケジュールが必要不可欠です。
10ステップと細かくなってしまいましたが、目標を達成するには最低限必要なステップと筆者は考えています。
一つひとつのやり方を見ていただければ、初心者であってもプロジェクトの実現は可能です。もしやり方に迷ったらどの段階にいるのか、どのステップが抜けているのか確認してみてください。
『合同会社あおに』では、豊富なクラウドファンディング支援実績を活かした「30分無料オンラインミーティング」を実施しています。またプロジェクトを実行したい企業様のために、伴走支援もおこなっております。
もう1記事読めそうであれば、こちらの記事がおすすめです。